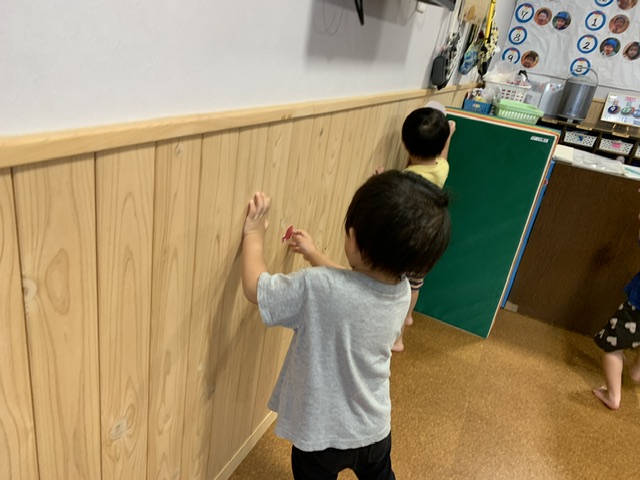お知らせ
2025.10.20
ブログ
ルールのある遊び(ゆり組)

- 2歳児の定型発達に「主張と気持ちのぶつかり合いを経験する」「ルールを守って遊ぶ」というものがあります。
この半年間の生活や遊びを通して「順番」や「待つ」といった簡単なルールや決まりに気づき守ろうとする姿が多く見られるようになりました。
しかし、2歳児は「なんでも自分でやりたい」という自我が芽生える時期でもあり自分の気持ちを抑えるのが難しいため、ルールを守れないこともあります。
それは自然なことなので、子どもたちの葛藤する気持ち等を受け止めながら、繰り返しルールや決まりを守ることの大切さを伝えているところです。
そこで、簡単なルールを理解し、他者との関わりの中で協調性や社会性を育くめるように、ルールのある遊びを取り入れました。
今回はそんな姿をお伝えしようと思います。
ルールのある遊びのねらい
ルールのある遊びの活動では以下のようなねらいがあります。
- ルールを守って遊ぶことの大切さを知る。
- 「捕まえられて嬉しい」「負けて悔しい」「まだやりたい」など自分の気持ちを豊かに表現する。
- 協調性やコミュニケーション能力を育む。
この中でも今回は「自分の気持ちを豊かに表現する」ことをねらいに活動しました。
ルールのある遊びに挑戦!
本格的にルールのある「しっぽ取り」や「宝(金魚)探し」はゆり組の子ども達にとって初めての経験。
「負けて悔しい!」「もう1回やりたい」などの気持ちを子ども達がどのように表すのかとワクワクしながら活動を始めました。
宝(金魚)探し
最初に行ったのは「宝(金魚探し)」。
大まかなルールは2つです。
- 大人が宝(金魚)を隠している間は手で目を隠す。
- 探す範囲(今回は絵本コーナーは✖️)を守る。
1の「目を瞑る」はゆり組の子ども達にとっては少々難しかったようでしたが、1人の子が避難訓練で教えた「ダンゴムシポーズ」をしたことにより他の子も真似してダンゴムシに。目を瞑っておくよりも簡単なこのポーズのおかげでほとんどの子が宝を隠す様子を見ないで待つことができていました。
2の探す範囲は私たち保育者も驚くほどに子ども達自身で守ることができており、約束を忘れて絵本コーナーに行ってしまった友達に対して「絵本コーナーは✖️だよ!」と教え合う姿も見られ成長を感じました。
2つのルールを守りながら、初めての遊びにワクワクした表情で取り組んでいました。
「あった!」と大小様々な金魚を見つけては、保育者へ嬉しそうに見せに来る子ども達。なかなか難しくて見つけられない場所も「ここの近くにあったよ~」とヒントを出すことで最後まで一生懸命探していました。
しっぽ取り
子ども達のルールを守りながら「宝(金魚)探し」をする様子を見て、「しっぽ取り」にも挑戦してみることにしました。
「しっぽ取り」の大まかなルールは4つです。
- 帽子をズボンの後ろ側に挟み、しっぽを作る。しっぽは手で抑えない。
- 鬼役は帽子を裏返してかぶる。
- 「よーいどん」の合図でスタートする。
- しっぽを取られた子は待機場所(今回はランチルームの絵本コーナー)へ移動する。
「宝(金魚)探し」に比べて少しルールが複雑になった「しっぽ取り」でしたが、保育者がデモンストレーションを見せたことでありルールの理解もスムーズにできていました。
回数を重ねるごとに、ルールの理解も深まり「鬼したい!」「もう1回しよう!」と楽しんで遊ぶことが出来ていました。
気持ちの表現
「しっぽ取り」の中では特にしっぽを取られて「悔しい!」という思いから大きな声で涙をしたり、「鬼がしたかったのにできない」など思い通りにならない経験をしたりと子ども達自身の感情が動かされる場面が多くありました。
2歳児の子ども達にとって、自分の感情や思いを言葉や態度で示すことはとても大切です。
私たち保育者は、“悔しい気持ち”や“思い通りにならない経験”を大切に「悔しかったね」「鬼がしたかったよね」と気持ちを受容し声を掛けることで表現の仕方を伝え、次は自分の言葉で伝えられるように援助しています。
子ども達にとっては「泣くこと」も自分の気持ちを表現する1つの手段であり、言葉で表現していくために必要な発達の過程でもあります。
これから年中、年長へ進級していくと感情のコントロールも身につけるようになっていきます。
その過程としても、今はそれぞれの方法で気持ちを表現することを大切にした保育を取り入れ、子ども達の自我の成長を見守っていきたいと思います。
文責:鮫島