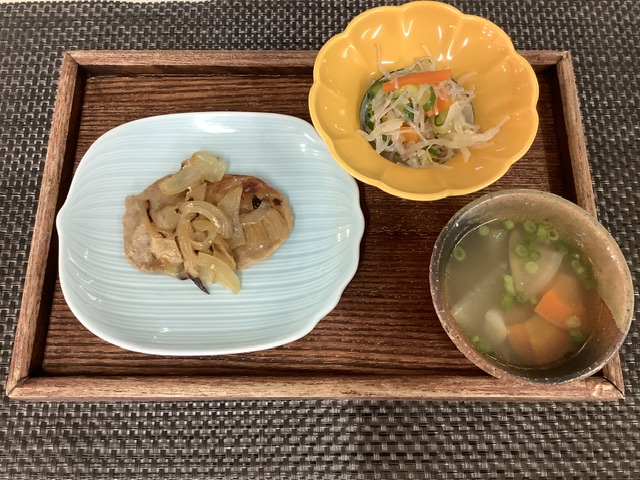お知らせ
2025.01.30
ブログ
散歩で育む協調性(凧あげに行ってきました♪)

新年を迎え、お正月ならではの遊びに触れてみよう!ということで、もも組ではみんなで凧を作りました。
凧の型紙に合わせてビニール袋をカット。透明のままでは寂しいので、好きなように絵を描き、ひらがな表を見ながら自分の名前を書き入れました。最近、もも組の子ども達はひらがなの読み書きに関心が高まっています。まだひらがなが書けない子も、ひらがな表を見ながら真似て書いたり、「僕の名前書いてみて」と大人に書いてもらったものをなぞったりして練習中です!凧に書き入れるとなると、失敗したくない気持ちから、力が入って体はカチコチ。一画書き終える度にふーっと緊張が解けていました。(書初めにも挑戦しました!さくら組に進級してそれぞれが頑張りたいことを、一文字一文字丁寧に、力強く書いています。ぜひ、クラスに展示している文字をご覧ください♪)
さて、いよいよ凧の仕上げです。しっかりと風を受け止められるように、ストローで骨作り。セロテープで入念に止めて、大人に凧糸をつけてもらい、自分だけのオリジナル凧が完成しました。「これってどうやって飛ぶのかな?」「早く飛ばしたいね!」と会話も弾みます。すぐにでも飛ばしに行きたい気持ちをぐっと抑え、凧を作った3日後に吉野いきいき公園に皆で歩いて凧上げに行きました。
ねらい①集団で歩くことを通して思いやりの気持ちや協調性を育む
これまでに散歩は数回繰り返してきました。始めのうちは、いつもと違う周囲の環境に気が散って列になって進むことがままなりませんでした。歩く速さの違いから大きく差が開いたり、前を歩く子の靴を踏んだりと、小さなトラブルも。普段は大人に手を引かれて進んだり、自分のペースに大人が合わせてくれるという状況で歩いているので、「友達と歩く速さを合わせる」ということは子ども達にとっては難しいことのようです。思い通りのスピードで歩けないことをストレスに感じる子もいたかもしれません。ですが、そこは有り余る元気と前向きさを持ち合わせているもも組の子ども達!回を重ねるごとに、「みんなで歩く」ということのコツをそれぞれ自分なりに掴んでいきました。前を歩く子との距離感を覚え、差が開いたと思ったら早歩きで詰めたり、ペアの子の手を引っ張ってリードしてくれたりする姿が見られるようになりました。ただ散歩に行っているという風に思われるかもしれませんが、集団で歩くことを通して、相手のことを思いやる気持ちが持てるようになります。もも組の子達も「○○くんの靴が脱げてるよ!」と友達が困っていることに気付き、大人に知らせる姿がありました。また、友達とペースを合わせて歩く、前の友達についていく、列から離れないということは、みんなが協力することで成り立つ行動であり「自分一人で勝手な行動をしない」という協調性を身に付けることに繋がります。すれ違う近隣の方々に「おはようございます」「こんにちは」と元気よく挨拶をし、返ってくる挨拶を嬉しそうに喜ぶ姿にも、成長と頼もしさを感じる時間でした。
ねらい②伝承遊びを楽しみ、気付いたことを伝え合う
公園に着くと、広々とした空間にテンションMAX!水筒などの荷物を置くなり「凧上げていい?!」と大人に確認して、皆全速力でダッシュしていました。走りすぎて息が切れていたその時、風の向きにうまくはまり、止まっていても風に乗って凧が上がると、「止まっていても飛ぶよ!」と一人が気付きました。また、走り出す時に誰かに凧を持っていてもらうと風を受けやすいことにも気付き、大人に「これ持ってて!」とお願いするようにもなっていきました。うまくいった経験を言葉で伝え合い、相手の話を聞いて取り入れ、自分も気付くことで、遊びがより楽しくなったり、嬉しい気持ちを通わせたりすることが出来たようです。まだまだ自分の思いを伝えたい気持ちが上回っていますが、相手の気持ちや考えにも思いを巡らせることが出来るようになると、より言葉で表現することが楽しくなり、豊かな語彙や表現が身についていくのだと感じます。子ども達の言葉での伝え合いを見守り、表現に迷う時には思いを汲み取って最適な言葉を提供し、その意味や表現方法の理解を深められるよう、サポート出来ればと思います。
凧あげは江戸時代、年の初めに子どもの出生を祝い、その無事な成長を祈る儀式として行われていたようです。子どもにとっても願い事を凧に乗せて「天まで届ける」という意味があったそう。風に乗って高く舞い上がっていたもも組の子ども達の凧ですから、この先、ますます元気に成長していく姿を見せてくれることでしょう!一日一日その成長を見逃さず、何事も一緒に楽しんでまいりたいと思います。今年もよろしくお願いいたします!文責:上岡