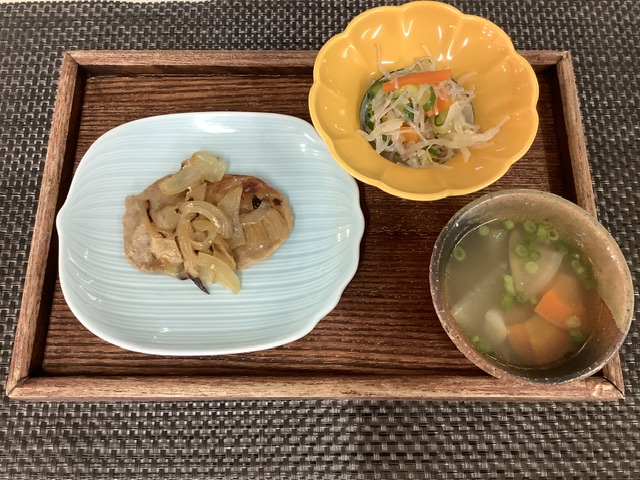お知らせ
2025.05.02
ブログ
さくらんぼ組(0、1歳児)話しことばを獲得するまで
はじめに
新年度がスタートし、1か月が経とうとしています。子どもたちも新しい環境での園生活に慣れてきました。私自身も、昨年度まで担任していた5歳児とは大きく発達段階の異なる0歳児、1歳児の子どもたち過ごすなかで新しい発見や驚きでいっぱいの日々を過ごしています。
なかでも一番興味深かったことは、予想以上に子ども達と言葉を介してのコミュニケーションが取れることです!1歳児クラスの子ども達は「パパ」「ママ」など初語が出始めたばかり。声に出せることばはまだ少ないかもしれません。しかし、「バイバイ」「手を洗おう」「お外」などのこちらからの日常の声掛けの意味が分かり、行動に移したりうなずいたりしてくれます。
子どもたちの様子を見ながら、話しことばの数と、声には出ずとも理解できていることばの数等に差があることに興味を持ちました。そこで、今回は子どもたちの「話しことば」に注目し、言葉の獲得までの過程や発達段階、それを知った上で大切にしていきたいことなどを書きたいと思います。
はなし言葉を獲得するまで
乳児期 ことばの獲得の準備期「泣く」「喃語」
子どもたちがことばを話し始める準備は産まれたときから始まっています。「泣く」ことで気持ちを表現する産まれたての赤ちゃんですが、成長するにつれて泣き方や声もバリエーションが増えていきます。やがて泣くこと自体が心理的意味をもつようになり。、生後6か月の赤ちゃんは1オクターブ半の音域のなかで泣き声を使い分けているようです。
その後、生後5か月~1歳ぐらいまでに基準喃語と呼ばれるおしゃべりが始まります。身近な大人と一緒にいることで安心するこの時期は、喃語に合わせて情動的に関わりおしゃべりをしてあげること子どもの心理発達においても重要といわれています。
「自律的ことば」から「話しことば」へ
やがて見たものを「マンマ」「コッコ」「ブーブー」などとこども達が独自に表現する時期へと移行します。具体的な場面を共有する身近な大人は何を指すのか理解しますが、大人の一般的な会話の中では使わないような言葉です。これらを『自律的ことば』といい、「ブーブー!」→「車がいるよ!」 「マンマ!」→「ごはんがたべたい!」など、子ども達は自分の欲求や情動を伝えようとします。
このような子ども独自の音声体系、意味的側面、コミュニケーション形式をもつ『自律的ことば』は、乳児期から幼児期への移行期(1歳~2歳はじめ)まで続き、どんな子どもの発達にもみられます。さらに「パパ」「ママ」など意味のあることば(初語)を話し始め、少ない単語もある程度コミュニケーションの手段としての役割を果たすことができるようになっていきます。また、事物の世界への関心がさらに高まり、形、色、長さ、重さなどの基本的性質を認知していきます。
1歳児クラスの子どもたちは、「どんな色が好き?」「あかー!」など歌が大好きです。また、絵本を読んでいると視覚的にとらえやすい情報(色や形)に、強い興味を持っていることも感じます。
そして「これ、なあに?」など大人も使う真の社会的・言語的コミュニケーションの手段としての『話しことば』が発達するのは、二語文を使い始めたり語彙が急増する2歳を過ぎてからといわれています。話しことばとして出てくるまでに、うたや絵本、大人との情緒的な関わりのなかでことばとその意味を蓄積していることがよくわかりました。
話しことばの3つの機能
やがて『話しことば』はコミュニケーションの手段としてだけではなく、より複雑な考えを形成するための手段として発達していきます。『話しことば』の機能として
- お互いの考えや情報を伝え合うコミュニケーションの道具
- 思考の道具
- 自分の感情や行動をコントロールする道具
などがあります。②の思考の道具としての『話しことば』には、4歳児が友達と遊んでいる時も自分に向かってしゃべるようなひとりごとも含まれます。ヴィゴツキーやピアジェの《内言》です。成長とともに、コミュニケーションの行為だったことばが内言に転化し、対自的思考行為の道具になることは、子どもたちの認識発達を理解するうえでも重要だと感じます。
豊かな「話しことば」のために
このような話しことばの育ちをサポートするために保育者ができることはなんでしょうか。子どもたちは、直接事物に触れる体験によって様々な学びを得ます。
その体験に保育者が感情をのせて言葉を添えることで、目の前の事物と言葉が一致します。例えば
・「いやだったね」「たのしいね」などの感情を表出する言葉
・「いっしょにしよう」「ありがとう」などのコミュニケーションの言葉
・数量、感覚や生活習慣、子どもの身近な社会に関する言葉
などが挙げられます。
今、初めて出会うことばのシャワーをたっぷり浴び、ことばとその意味を蓄積している子どもたち。
やがて私たち保育者と一緒に共有したことばを通して、友達に感情を伝えたり、相手の感情を理解することに役立つかもしれません。
また、自己の思考を深め、話し合い活動でよりよいアイデアを友達と出し合うかもしれません。
そんな近くて遠い子ども達の姿を想像すると、さくらんぼ組の子どもたちが初めて出会う体験に言葉を添えるということは、とても貴重で重みのある役割だと感じます。
日々の積み重ねの中で、豊かなことばを使ってやりとりしていくことを今後も大切にしていきたいです。
文責:椎屋
参考文献
『ヴィゴツキー入門(2006)』柴田義松 子どもの未来社
『手に取るように発達心理学が分かる本(2009)』小野寺敦子 株式会社かんき出版
『保育者の関わりの理論と実践~教育と福祉の専門職として(2019)』 高山静子 エイデル研究所
『保育内容 5領域の展開~保育の専門性に基づいて(2022)』高山静子 郁洋社