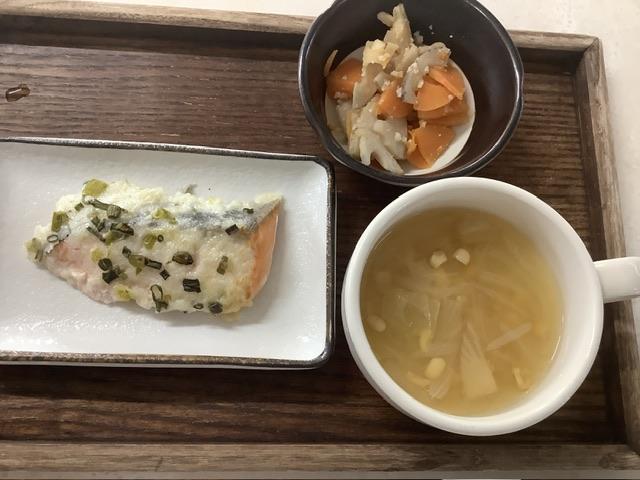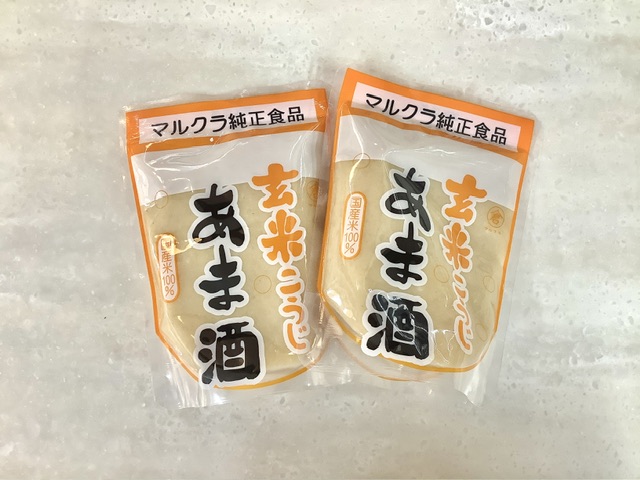お知らせ
2022.10.24
ブログ
きく組(3歳児)色を作り出す

9月に行なった2回の色水遊び。単色のきれいさ・濃淡の違いに気付いたり、色の混ざりを楽しむ機会となりました。
色水遊びのきっかけ
仮園舎前の柵に咲いていた紫色のあさがお。
遊んでいる時にふと見つけた子どもたちは、両手にたくさんの花を摘んでいました。
そこで、大人が容器と水を準備し、机にそっと置くと…色水遊びへ発展!花の数を増やすと色が濃くなることや、水の性質を遊びを通して学ぶことができました。


2回目の色水遊び

全て大人発信ではなく、
『子どもたちが自ら気付き、興味を持つ→遊びは広がる』
という過程を大切にしたく、大人はきっかけ作りをしました。
まず、靴箱の上に7色の色水を置きました。
子ども達はすぐに気付き、「なにこれ!」「どうやって作ったの?」「色水遊びしたい!」と興味を示しました。
そこで、大人が赤・青・黄の色水を準備し、活動開始。
子どもたちは、ペットボトルや透明カップなどに色を混ぜて新しい色を作り出します。中には「赤を2杯、青を1杯」など分量を考えている子もいました。

同じ色でも様々な濃淡ができ、色水を見比べたり、無色透明の水を『まほうのみず』と名付け、色水に加えて色が薄くなったり量が増えたりすることにも気付いていました。
「様々な色の水ができたからみんなが作った色水を並べてみる?」
と提案しましたが、子どもたちは色水を混ぜること、さらに新しい色を作ることなど、色水の変化に夢中でした。
子どもが遊びこむ姿に引き込まれ、探求心と集中力にすごいと思わされた場面でした。


子ども達は遊びの中で、探求する経験、量をはかる経験などをしています。あそんでいるうちに、問いが生まれ、自分なりに試行錯誤する探求の中で、発見が生まれているのです。
子ども達発信の遊びが展開されるよう日常の中での子どもの気付きをすぐキャッチしたり、子どもたちが自ら気付き遊びに関われるようなきっかけ作りをおこなったりしていきたいです。
文責:市来
参考文献:「対話」から生まれる乳幼児の学びの物語
編著 大豆生田啓友